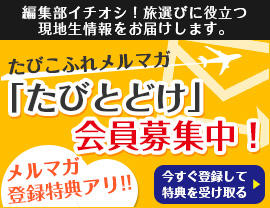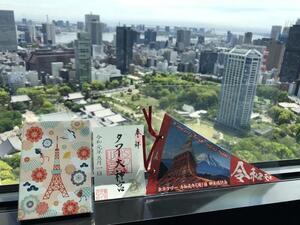公開日:
最終更新日:
ライター・中尾の『日本百名山』登山レポート(現在32座)

<トップ画像:燧ヶ岳/2024年4月28日撮影>
こんにちは!たびこふれライターの中尾です。
2022年11月から始めた僕個人の日本百名山の登山シリーズ。2025年8月現在、32座となり、順調に登山を続けています。
僕自身、登山に関しては初級者レベル。簡単な山で日帰りで登れる山を中心に登山を続けています。僕のレベルで100座というのは夢のまた夢で、半分登れれば万々歳かなと思っています。
この記事では、これまでに登った日本百名山を順番に記録していきます。
目次
- 1座目:地獄と天国を体験した月山登山(山形県)
- 2座目:雨の中をひたすら登った大山(鳥取県)
- 3座目:特攻機が目指して飛んだ開聞岳(鹿児島県)
- 4座目:ダイナミックな霧島連山の主峰・韓国岳(宮崎県)
- 5座目:命がけで登った阿蘇山(熊本県)
- 6座目:GWでも雪山!尾瀬の至仏山(群馬県)
- 7座目:御釜を眺めながら楽々登山・蔵王山(山形県)
- 8座目:雲上の楽園まで急登!会津駒ヶ岳(福島県)
- 9座目:もう嫌だ!登りも下りも苦労の連続!燧ヶ岳(福島県)
- 10座目:風の怖さを知った八甲田山(青森県)
- 11座目:楽して登ろうと思ったが...岩木山(青森県)
- 12座目:初心者でも登れる百名山があった!八幡平(岩手県)
- 13座目:ケーブルカーかロープウェイで登れる筑波山(茨城県)
- 14座目:霧ヶ峰(車山)を雪中ハイキング(長野県)
- 15座目:美ヶ原(王ヶ頭)のパノラマコースを雪中ウォーキング(長野県)
- 16座目:初級者向だけどしっかりした装備で登りたい赤城山(群馬県)
- 17座目:大迫力の利尻山(北海道)
- 18座目:神々の遊ぶ庭・大雪山旭岳(北海道)
- 19座目:石鎚山はまさに修行の山(愛媛県)
- 20座目:紅葉の絨毯を見に安達太良山へ(福島県)
- 21座目:ダイナミックな爆裂火口を有する磐梯山(福島県)
- 22座目:西吾妻山...初級者向け?いえいえ結構大変な山でした(山形県・福島県)
- 23座目:天空の絶景ロードを見たくて剣山へ(徳島県)
- 24座目:大台ヶ原山を周回するはずが...(奈良県・三重県)
- 25座目:伊吹山はヤマトタケルが見守る山岳信仰の山(滋賀県・岐阜県)
- 26座目:摩訶不思議な世界が広がる久住山(大分県)
- 27座目:祖母山は道迷いに注意が必要(大分県・宮崎県)
- 28座目:最初から最後まで急登が続く男体山(栃木県)
- 29座目:天空のお花畑が登山者を魅了する日光白根山(栃木県・群馬県)
- 30座目:北アルプスの名峰・白馬岳へのアプローチ(前編)
30座目:北アルプスの白馬岳への絶景ロードを登る(中編)
30座目:白馬岳山頂から白馬大雪渓を下る(後編) - 31座目:美しき天空の花回廊・鳥海山へは晴天時を狙って!(秋田・山形)
- 32座目:アルペンルートの最高点・室堂から登る立山(富山)
1座目:地獄と天国を体験した月山登山(山形県)

■登山日:2022年8月27日
山形県の月山(がっさん)は僕の記事で2度紹介しました。2022年、2011年から登り続けた月山登山が10回目を迎えたので、「今後は登山の視野を広げていこう」と思い、日本百名山への挑戦を決めました。
その1座目として月山の登山レポートをお送りします。
>>『1座目は地獄と天国を体験した月山登山(山形県)』はこちら
2座目:雨の中をひたすら登った大山(鳥取県)

■登山日:2022年11月5日
鳥取県にそびえる大山(だいせん)は伯耆(ほうき)富士と呼ばれる山容がとても美しい山。中国地方で最も標高が高い独立峰です。見る角度によって見え方がまったく異なるので、登山者だけでなく、観光客を魅了する山でもあります。今回は『夏山登山コース』から頂上を往復しましたので、詳しくレポートします。
>>『2座目は雨の中をひたすら登った大山(鳥取県)』はこちら
3座目:特攻機が目指して飛んだ開聞岳(鹿児島県)

■登山日:2023年2月11日
開聞岳(かいもんだけ)は標高924mと小さな山ですが、海抜0mから一気に標高を上げる円錐形の山容は別名「薩摩富士」とも呼ばれる美しい山です。
富士山に似た美しい山なので、昭和20年の戦時中は、知覧から多くの特攻機が飛び立ち、薩摩半島の南端に位置する開聞岳を目指し、最後に別れを告げ、南(沖縄)に針路をとったと言われています。僕はそんなことを考えながら登りましたが、地元の方々をはじめ、日本百名山を目指す登山者で賑わっていました。
>>『3座目は特攻機が目指して飛んだ開聞岳(鹿児島県)』はこちら
4座目:ダイナミックな霧島連山の主峰・韓国岳(宮崎県)

■登山日:2023年3月18日
韓国岳(からくにだけ)は標高1,700mを誇る霧島連山(きりしまれんざん)の最高峰。えびの高原東南にそびえ、直径900m、深さ300mの火山湖を持つダイナミックな山です。
韓国岳の山名は、晴れた日に山頂から遠く韓国まで見渡せると言われていることからこの名前が付いたそうです。何よりも韓国岳山頂からのダイナミックな景色は誰もを魅了すると言われています。
初級者向けの登山道もあり、僕もダイナミックな景色を求めて登ってきました!
>>『4座目はダイナミックな霧島連山の主峰・韓国岳(宮崎県)』はこちら
5座目:命がけで登った阿蘇山(熊本県)

■登山日:2023年3月19日
熊本県の阿蘇山(あそさん)は誰でも一度は聞いたことがある山だと思います。
九州のほぼ真ん中にあり、桜島と同じく火山。常に火口からモクモクと噴煙が上がっているというイメージだと思います。僕も中学の修学旅行で行ったことがあり、当時は噴火口をのぞきこんだ記憶があります。しかし、僕も含めほとんどの方のイメージはここまでではないでしょうか...。僕はつい最近まで阿蘇山に登山できるとは思っていませんでした。
日本百名山でもある阿蘇山の最高峰・高岳(たかだけ)に登ってきましたので、阿蘇山がどんなところなのかをイメージしていただければ幸いです。
6座目:GWでも雪山!尾瀬の至仏山(群馬県)

■登山日:2023年5月1日
日本百名山シリーズの6座目は、至仏山(しぶつさん)。尾瀬ヶ原の西側にどっしりと腰をおろした大きな山です。標高2,228mの頂上から、眼下に尾瀬ヶ原、その先に燧ヶ岳(ひうちがたけ)、さらに遠くに会津駒ヶ岳や日光の山々、新潟の山々まで360度の眺望を楽しめる山として人気があります。
世間はゴールデンウイークですが、至仏山はまだまだ雪山。その時の様子をレポートします。
>>『6座目はGWでも雪山!尾瀬の至仏山(群馬県)』はこちら
7座目:御釜を眺めながら楽々登山・蔵王山(山形県)

■登山日:2023年8月11日
日本百名山シリーズ7座目です。蔵王山(ざおうさん)は山形県と宮城県にまたがる火山群の総称のこと。主峰は熊野岳(くまのだけ)で標高1,841mです。
蔵王山というより、蔵王という名で知られるこの山は、やはり御釜(おかま)と樹氷が有名。登山ルートも登山口も様々なので、初級者から上級者まで登山を楽しむことができる山でもあります。
今回、僕が登ったルートは蔵王山頂レストハウスから熊野岳往復コースです。天気が良ければ御釜を見ながらハイキング気分で登ることができるのでとても人気のルートでもあります。
>>『7座目は御釜を眺めながら楽々登山・蔵王山(山形県)』はこちら
8座目:雲上の楽園まで急登!会津駒ヶ岳(福島県)

■登山日:2023年8月27日
南会津の名峰・標高2,133mの会津駒ヶ岳(あいづこまがたけ)に登りました。
山頂付近一帯は広大な湿原が広がり、それまで急登を登ってきた疲れが一気に吹き飛びます。尾瀬の玄関口である桧枝岐村(ひのえまたむら)をベースに日帰り登山ができますので、尾瀬へ向かう前に登ってみてはいかがでしょうか。
9座目:もう嫌だ!登りも下りも苦労の連続!燧ヶ岳(福島県)

■登山日:2023年8月28日
東北最高峰は福島県にそびえる標高2,356mの燧ヶ岳(ひうちがたけ)です。眼下には尾瀬ヶ原や尾瀬沼を見渡すことができ、尾瀬ヶ原をはさんで至仏山(しぶつさん)と相対している高山です。
至仏山はなだらかな山容なので女性的なのに対し、燧ヶ岳は人を寄せつけないような険しい山容なので男性的な山だと僕は思います。2023年のゴールデンウイークに至仏山に登り、続いて燧ヶ岳にも登ろうと計画していましたが、山小屋の人に「雪山時期はかなり厳しい山行になるので、時期をずらして経験者と登るように」とアドバイスを受けました。
山から雪がなくなり、そして燧ヶ岳登山経験者に同行する機会に恵まれましたので登りましたが、無冠雪期でもかなり厳しい山行になりました。
登山道の様子などの詳細を記事にしましたので、今後登山される方の参考になれば幸いです。
>>『9座目は、もう嫌だ!登りも下りも苦労の連続!燧ヶ岳(福島県)』はこちら
10座目:風の怖さを知った八甲田山(青森県)

■登山日:2023年10月3日
八甲田山は単体の山ではなく、いくつものピークが連なり八甲田連峰を形成しています。その主峰は大岳(おおだけ)標高1,585mです。決して高い山ではありませんが、冬は豪雪地帯になり、過去に「八甲田雪中行軍遭難事件」が発生した山としてもその名を耳にされた方も多いはず。
雪とは関係のない7月にアタックしましたが、悪天候で中止。(天候が悪いと僕は登りません。)再度10月にアタックしましたが...。やはり自然をなめたらあかんと思い知らされた登山になりました。カッコ悪いところをお見せすることになりますが、ぜひ最後までご覧ください。
>>『10座目は風の怖さを知った八甲田山(青森県)』はこちら
11座目:楽して登ろうと思ったが...岩木山(青森県)

<写真提供:青森県観光情報サイト>
■登山日:2023年10月8日
岩木山はリンゴの名産地で知られる青森県西部の津軽平野にそびえる母なる山。津軽富士とも呼ばれ地域の人々から愛されています。
岩木山への登山道は5ルートありますが、僕は8合目まで車で上がり、さらにリフトを使って9合目まで行き、そこから頂上を目指しました。9合目まで文明の利器を使って移動したのだから、残りはさぞ楽なのだろうと高をくくっていたのですが、山はそう甘くはありませんでした。大きな岩がゴロゴロ、小さな石がコロコロ...。何度も転倒しそうになりながら登頂しました!
>>『11座目は楽して登ろうと思ったが...岩木山(青森県)』はこちら
12座目:初心者でも登れる百名山があった!八幡平(岩手県)

<写真提供:岩手県公式観光サイトいわての旅>
■登山日:2023年10月9日
八幡平は山頂直下まで車で行くことができ、駐車場から30分程度で山頂まで行くことができる日本百名山の中で誰でも登れる山。でも、ただ登るだけではもったいない。八幡沼など湖沼地帯をぐるっと一周ハイキング気分で歩くのをおすすめします。登山後は、周辺に点在する秘湯に入浴するのも最高です。
>>『12座目は初心者でも登れる百名山があった!八幡平(岩手県)』はこちら
13座目:ケーブルカーかロープウェイで登れる筑波山(茨城県)

■登山日:2024年1月14日
日本百名山の中で一番標高が低い筑波山(877m)。頂上は男体山と女体山の2つの峰があります。麓からはケーブルカーとロープウェイで誰でも簡単に山頂直下まで行くことができます。僕はケーブルカーを利用しましたが、山頂駅から男体山まで往復30分、女体山まで往復30分のちょっぴり登山。山頂からの眺望は富士山やスカイツリー、信州や北関東の山々を見渡すことができます。
>>『13座目はケーブルカーかロープウェイで登れる筑波山(茨城県)』はこちら
14座目:霧ヶ峰(車山)を雪中ハイキング(長野県)

■登山日:2024年2月11日
霧ヶ峰の最高峰は車山(くるまやま)で標高1,925mあります。そこそこ標高が高い山なのに遊ぶ山...。それは行ってみるとすぐに「ああ、なるほど」と感じると思います。ビーナスラインが真ん中に通り、夏になるとニッコウキスゲが咲き誇り、湿原が広がり、牧歌的な光景が広がる霧ヶ峰。
今回は一面銀世界の真冬に登りましたので、夏とはまた違った顔を見せてくれました。気軽にアクセスできる「遊ぶ山」霧ヶ峰(車山)を紹介します。
>>『14座目は霧ヶ峰(車山)を雪中ハイキング(長野県)』はこちら
15座目:美ヶ原(王ヶ頭)のパノラマコースを雪中ウォーキング(長野県)

■登山日:2024年2月11日
美ヶ原はビーナスラインの終点地域にある標高2,000mの高原地帯。そこをテクテク歩いて行くと日本百名山の王ヶ頭(おうがとう)に行くことができます。王ヶ頭へは登山と言うよりウォーキング気分で誰でも日本百名山に登ることができます。特に急登もなく、パノラマコースと呼ばれる登山道も整備されているので、真冬でも天候さえ良ければ、360度銀世界の中をウォーキングすることが可能です。
>>『15座目は美ヶ原(王ヶ頭)のパノラマコースを雪中ウォーキング(長野県)』はこちら
16座目:初級者向だけどしっかりした装備で登りたい赤城山(群馬県)

■登山日:2024年4月29日
尾瀬を訪問した後に登りました。登山口から黒檜山山頂まで急登を登り切り、その先は尾根道をアップダウンを繰り返しながら、駒ヶ岳山頂へ。最後はひたすら駐車場まで下る時計回りコースを進みました。天候は晴れていたものの、霞がかかっていて遠くの山々まで見えなかったのが少し残念。標高1,828mながら登りごたえがある名山でした。
>>『【日本百名山】16座目は初級者向だけどしっかりした装備で登りたい赤城山(群馬県)』はこちら
17座目:大迫力の利尻山(北海道)

■登山日:2024年7月14日
人生初の北海道登山です。対岸の稚内からも素晴らしい山容を見せてくれる利尻山への挑戦。標高差約1,500mを約9時間かけて登る過酷な登山。雲を突き抜け正面に山頂が見えた時はとても感動しました。しかし、下り坂で膝を痛め、翌日の大雪山登山に影響しました。それでもこれだけダイナミックな山に登れたのは自分でも感動でした。また登りたいかと言うと...。
>>『【日本百名山】17座目は大迫力の利尻山(北海道)』はこちら
18座目:神々の遊ぶ庭・大雪山旭岳(北海道)

■登山日:2024年7月15日
大雪山旭岳へはロープウェイを利用すればとてもアクセスしやすい山です。モクモクと噴煙が上がるのを横目に北海道最高峰へ足を進めます。山頂は風が強かったので、時折ガスが抜け、大雪山系の山々がチラッと姿を現しては消えの繰り返しでした。前日に登った利尻山の影響で膝が曲げにくくなり、下山途中で動けなくなり、足を引きずりながら何とか下山しました。これも良い思い出です。
>>『【日本百名山】18座目は神々の遊ぶ庭・大雪山旭岳(北海道)』はこちら
19座目:石鎚山はまさに修行の山(愛媛県)

■登山日:2024年9月30日
修行の山と言われるだけあって、鎖場は大迫力がありました。言い訳をすれば登山者が少なかったので、鎖場には挑戦せず、迂回路を通りましたが、なんのなんの迂回路も崖っぷちでとても怖い思いをしました。さらに本来の頂上である天狗岳には行かず...。もっと鍛えてから再訪したいと思います。
>>『【日本百名山】19座目の石鎚山はまさに修行の山(愛媛県)』はこちら
20座目:紅葉の絨毯を見に安達太良山へ(福島県)

■登山日:2024年10月11日
ゴンドラを利用すれば誰でも片道1時間程度で山頂に立てる山。ですが、登山道は泥沼化しているので登山靴は防水機能がついているかどうかを確認する必要があります。時間があれば沼ノ平と呼ばれる爆裂噴火口にも立ち寄りたいです。
>>『【日本百名山】20座目は紅葉の絨毯を見に安達太良山へ(福島県)』はこちら
21座目:ダイナミックな爆裂火口を有する磐梯山(福島県)

■登山日:2024年10月12日
磐梯山は会津の母なる山として親しまれていますが、過去に大きな噴火を起こし、現在の山容になった山でもあります。登山道は整備されていて、見た目より登りやすい山だと思いました。山頂からは360度の眺望を楽しむことができる素晴らしい山です。
>>『【日本百名山】21座目はダイナミックな爆裂火口を有する磐梯山(福島県)』はこちら
22座目:西吾妻山...初級者向け?いえいえ結構大変な山でした(山形県・福島県)

■登山日:2024年10月13日
西吾妻山は広大な吾妻連峰の主峰。2,035mの山頂からさぞかし素晴らしい眺望を...。眺望はありませんでした。大きな岩と泥沼の登山道に転倒すること2回。とても初級者向けのコースではありませんでした。
>>『【日本百名山】22座目は西吾妻山...初級者向け?いえいえ結構大変な山でした(山形県・福島県)』はこちら
23座目:天空の絶景ロードを見たくて剣山へ(徳島県)

■登山日:2024年10月27日
リフトを利用すれば30分程度で山頂に立つことができる剣山。剣山の魅力は山頂から次郎笈(じろうぎゅう)へと延びる天空の尾根道。これを見るためだけに登る価値がある山です。
>>『【日本百名山】23座目は天空の絶景ロードを見たくて剣山へ(徳島県)』はこちら
24座目:大台ヶ原山を周回するはずが...(奈良県・三重県)

■登山日:2024年11月2日
大台ヶ原は時計回りに周回するのがオススメの見どころ満載の山。しかし、全国屈指の多雨地帯なので、僕が訪問した時も雨。なので、周回せず山頂までの往復だけにしました。次回こそは!
>>『【日本百名山】24座目は大台ヶ原山を周回するはずが...(奈良県・三重県)』はこちら
25座目:伊吹山はヤマトタケルが見守る山岳信仰の山(滋賀県・岐阜県)

■登山日:2024年11月3日
日本百名山の中で誰でも簡単に山頂に立てる山。車のドライブを兼ねて山頂までハイキング気分で登られる方が多いです。しかし、冬場は誰も寄せつけない豪雪地帯となります。
>>『【日本百名山】25座目の伊吹山はヤマトタケルが見守る山岳信仰の山(滋賀県・岐阜県)』はこちら
26座目:摩訶不思議な世界が広がる久住山(大分県)

■登山日:2024年11月15日
最初に息が上がるくらいの急登を登り、その先は尾根を登ったり下りたりの繰り返し。途中、不思議な光景が広がる九重連山の山々に抱かれながら進み、最後は山頂まで急登を登ります。四季それぞれの顔を見せてくれる九重連山は登山者にとても人気の山でもあります。次はミヤマキリシマが咲く頃に九重連山を縦走してみたいと思っています。
>>『【日本百名山】26座目は摩訶不思議な世界が広がる久住山(大分県)』はこちら
27座目:祖母山は道迷いに注意が必要(大分県・宮崎県)

■登山日:2024年11月16日
周囲の阿蘇山、九重連山、霧島連山に比べ、登山者も少ない穴場的な百名山。山頂からは360度の大パノラマが楽しめます。ただし千間平コースは尾根上に出ると晴れていても道迷いに十分気をつけないといけません。ピンクリボンを目印に慎重に登りましょう!
>>『【日本百名山】27座目の祖母山は道迷いに注意が必要(大分県・宮崎県)』はこちら
28座目:最初から最後まで急登が続く男体山(栃木県)
■登山日:2025年6月28日
世界文化遺産・日光の社寺がある日光市からいろは坂を上がると華厳の滝があり、中禅寺湖が広がります。その中禅寺湖畔にそびえる男体山の山頂には日光二荒山神社が鎮座しています。まさに神の山にふさわしい山容は見た目とは裏腹に最初から最後まで急登が続く修行の山。山頂には剣が天に向かってそびえ登ってきた登山者を出迎えてくれます。
>>『【日本百名山】28座目は最初から最後まで急登が続く男体山(栃木県)』はこちら
29座目:天空のお花畑が登山者を魅了する日光白根山(栃木県・群馬県)
■登山日:2025年6月29日
関東以北では最高峰の日光白根山。雪解けとともに高山植物が一面に咲き誇る花の百名山としても有名です。ロープウェイを利用して2,000m地点から開始する登山ですが、結構登りごたえのある山です。苦労して登った先には楽園と素晴らしい眺望が広がります。
>>『【日本百名山】29座目は天空のお花畑が登山者を魅了する日光白根山(栃木・群馬)』はこちら
30座目:北アルプスの名峰・白馬岳(長野県・富山県)

■登山日:2025年7月19日~20日
初めての北アルプス。知人に「白馬岳は絶対に感動するから!」と紹介され登山。天候に恵まれ、絶景を眺めながらの登山は、それまでの疲れも吹っ飛び感動しっぱなしでした。登山をやっていて良かったなと思った山行でした。
>>『【日本百名山】30座目は北アルプスの名峰・白馬岳へのアプローチ(前編)』はこちら
>>『【日本百名山】30座目は北アルプスの白馬岳への絶景ロードを登る(中編)』はこちら
>>『【日本百名山】30座目は白馬岳山頂から白馬大雪渓を下る(後編)』はこちら
31座目:美しき天空の花回廊・鳥海山へは晴天時を狙って!(秋田・山形)

>>【日本百名山】31座目は美しき天空の花回廊・鳥海山へは晴天時を狙って!(秋田・山形)
32座目:アルペンルートの最高点・室堂から登る立山(富山)

>>【日本百名山】32座目はアルペンルートの最高点・室堂から登る立山(富山)
僕の日本百名山登山はまだまだ続きます。
関連記事
Ranking国内エリア記事ランキング
-

中尾勝
- 旅が大好き!国内海外を問わず飛び回っていますが、海外へは2011年に渡航して以来、出国していません。今は原点に戻り国内を旅しながら日本の良さを体感中。