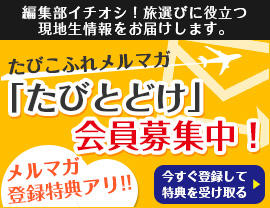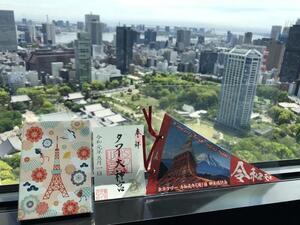公開日:
最終更新日:
居合道と剣道は別もの?居合道発祥の地で「本物の居合道」に触れる【山形】

居合道を知っていますか?
私が思い浮かぶのは、立てられた筒状のたたみ表を斜めに切り下げるあのデモンストレーションです。昔テレビでやっていた「新春芸能人かくし芸大会」などで見た記憶があります。確か居合抜きって言ってましたっけ。あれを見て私は思ってました。
「居合って実践では強いんだろうか?」と。
今回、居合道発祥の地である出羽の国(現在の山形県村山市)の「本物の居合」を見てきました。私は剣道も居合道も似たようなものかと思っていましたが、別のものであることがわかりました。そのことをご紹介したいと思います。
目次
居合道のはじまり
今をさかのぼること約450年前、室町時代の末期に現在の山形県村山市で居合道は生まれました。林崎甚助重信公が居合の始祖と言われています。
林崎甚助は子供の頃、父を闇討ちで殺され、仇討ちの為に、武術を修行し、19歳の時に見事に仇を討ち果たしました。その後、林崎は諸国を廻って修行する傍ら多くの弟子も育てました。林崎が編み出した居合の流派が神夢想林崎流(しんむそうはやしざきりゅう)といい、その後流派が分かれて現在に至っているそうです。
居合道と剣道の違い
剣道は基本的に剣(刀)を抜いて相手と対峙し、構えるところから始まります。(もちろんそれまでの所作、礼儀作法なども剣道に含まれますが)
それに対して居合道は座っている状態、刀は鞘(さや)の中に納まっている状態で敵が至近距離から襲ってくるという場面を想定して型が組まれています。よく時代小説などで「やつは居合を使うぞ、気をつけろ」というセリフが出てきますが、居合道は剣の技術という点では初撃がすべて、といっていい武道といえるでしょう。
ちなみに居合の達人として有名なのは幕末に登場した薩摩の桐野利秋です。(彼は「人斬り半次郎」と呼ばれた剣客で、雨だれが軒から地面に滴り落ちるまでの間に三度抜刀して三度鞘に納めたとの逸話が残っているようです)
「初撃がすべての武術では、それを外せば負けてしまうのでは?」つまり、戦い方としては完璧ではないのでは?と感じた人もいらっしゃるかもしれません。(私はそう思いました)
居合道が目指すところは、剣術の技術向上よりも、精神性を鍛え人格を形成することを最終目標としています。
剣道も礼儀作法、精神修行を重視していますが、居合道の方がさらにその精神性の鍛練を重視しているということでしょう。
技術よりも心を鍛える
剣道は刀を抜いて向き合い、戦いが始まるという臨戦体勢からの武術ですが、居合道は臨戦体勢ではない平時の状態で敵が襲い掛かってきた時への対応です。
強靭な精神力、研ぎ澄まされた集中力の鍛練が必要です。物事に動じない心を作る、とも言い変えられるでしょう。
圧倒的な精神力の強さで相手の戦意を喪失させる。
つまり「刀を抜かずに戦いに勝つ」ことを目指している、これはもう単なる武術やスポーツではありません。
日本人よりも外国人に理解されやすい居合道
居合道はその精神を外国人にとても関心を持たれるそうです。それは居合道の精神性が宗教に近いといえるからという面があるからでしょう。
外国人はキリスト教、イスラム教、仏教など宗教が人々に根づいている為、日本人よりも居合の精神を理解しやすいのかもしれません。
居合抜刀術のデモンストレーション
日本では見世物のイメージが強い居合抜刀術ですが、実際に目の前で見た印象は、張り詰めた緊張感のあるものでした。

真剣の凄みが想像以上に伝わってきました。
それでは実際に目の前で見た居合抜刀術のデモンストレーションを動画でご紹介しましょう。
その①
その②
その③
わかりやすい居合道という意味からこの抜刀術はよく引き合いに出されますが、筒状の畳を切るデモンストレーションは居合道のごくごく一部であるに過ぎません。
こちらが真剣で真っ二つに切られた畳面です。これで大人の太ももくらいの強度があるそうです。

最後に
デモンストレーションを見せていただいた阿部先生によると「居合道を修行していると、死ぬことが怖くなくなります」
村山市では居合抜刀術の体験修行も可能です。単に刀の扱い方を習うのではなく、その精神性も含め体験できます。
体験とは言え、必ず道着を着て行います。道着も居合道に触れる際の大切なアイテムと言えるのでしょう。
居合道の発祥の地、村山市では子供の頃から居合に慣れ親しんでいて、とても身近な存在なのだそうです。
スポーツや武道は身体と心を鍛えます。
居合道は精神修行を一番重視しており、何事にも動じない人格を作っていく「道」なのです。
世の中が不安定なこの時代だからこそ、「居合道」の価値と重要性が増しているのかもしれません。
Ranking山形記事ランキング
-

シンジーノ
- 3人娘の父で、最近は山歩きにハマっているシンジーノです。私は「お客さまが”笑顔”で買いに来られる商品」を扱う仕事がしたいと思い、旅行会社に入って二十数年。今はその経験を元にできるだけ多くの人に旅の魅力を伝えたいと“たびこふれ”の編集局にいます。旅はカタチには残りませんが、生涯忘れられない宝物を心の中に残してくれます。このブログを通じて、人生を豊かに彩るパワーを秘めた旅の素晴らしさをお伝えしていきたいと思います。